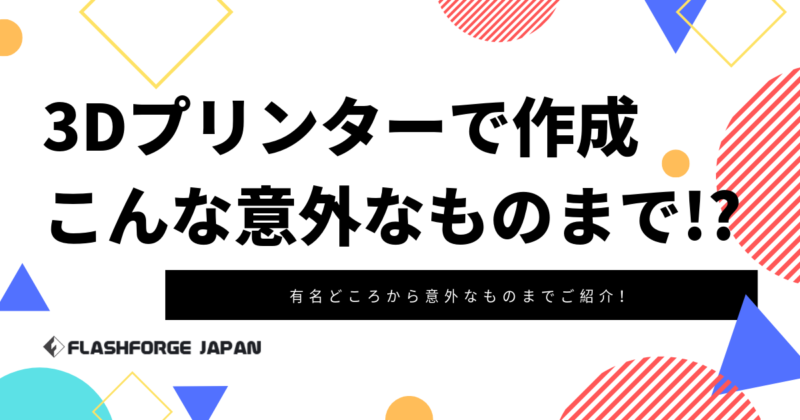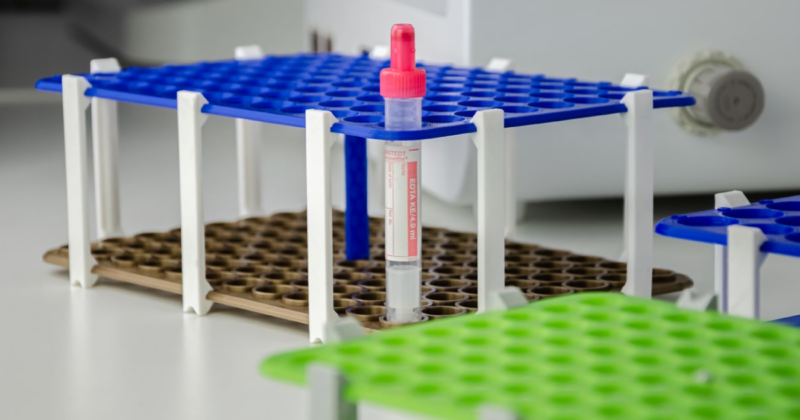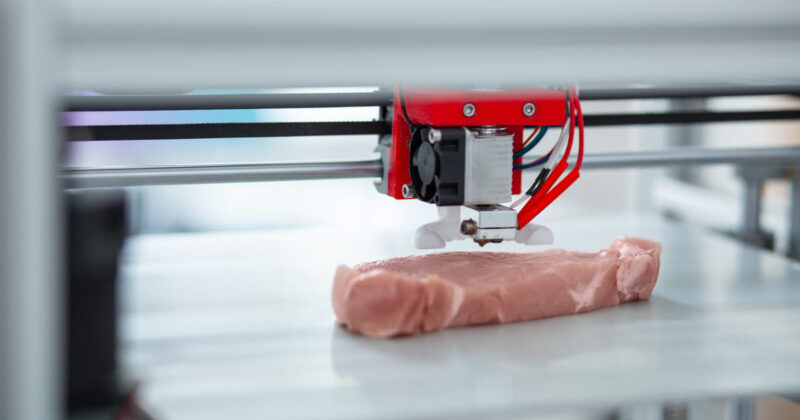-
3Dプリンター
- 公開日:2022.7.11
- 更新日:2022.7.13
3Dプリンターで住宅ローンがなくなる?活用事例や料金など徹底解説

日本国内の持ち家率は60.9%であり、残りの40%ほどの人は自宅を持っていません。(平成20年、総務省統計局より)価格が高く、簡単に手に入れることはできないことも大きな理由です。
そんな中で注目されているのが、3Dプリンターで作った住宅です。
従来の住宅と比べて価格が安いことから、多くの人が購入できるようになると考えられています。しかし、3Dプリンターで作った住宅といわれてもイメージしにくいという人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、3Dプリンターで作った住宅の活用事例や料金などを徹底的に解説していきます。
ページコンテンツ
住宅の購入は30年ローンが一般的
住宅は人生で最も高価な買い物であり、新築では30年ローンを組まないと購入できない場合がほとんどです。
そもそも住宅の価格が高額なのは日本の土地は狭く、災害が多いことから中古物件が少ないことなどが主な理由です。
職業が安定しない現代での長期ローンは、リスクが高いと感じられるでしょう。
近年は輸入材の価格が高騰している(ウッドショック)
もともと高額な住宅ですが、新型コロナ渦以降は輸入材の価格が高騰しています。輸入材の価格高騰により住宅の価格も上昇したほか、工期遅れなどの問題も発生しています。
以下は、ウッドショックの主な原因です。
- アメリカでのテレワーク普及により、郊外での住宅需要が高まっている
- 中国の景気回復による木材需要の高まり
- 新型コロナウイルスまん延防止のため輸入コンテナの取り扱いが減少
ほかにも、新型コロナウイルスの影響で労働者が不足したことで、伐採や輸送が滞っていることも原因といわれています。
輸入材価格、今後の見通しは?
輸入材価格の今後の見通しはわかりません。世界市況の展開は誰にも予想できないので、輸入材価格の推移を注意深く見るほかにないのです。そうした世界の流れにあって、今、3Dプリンターで建設した住宅が注目されています。
では、どのようにして3Dプリンターで住宅を製作しているのか事例を次でご紹介します。
一般向け3Dプリンター住宅の事例
2カ国における一般向け3Dプリンター住宅の事例をご紹介します。
- アメリカ
- 日本国内
上から順番に見ていきましょう。
3Dプリンター大国のアメリカでの事例
アメリカでは、もともとミレニアム世代を中心に郊外型住宅の購入が増えていました。加えて、コロナ対策として金利を実質ゼロに誘導したため住宅ローンが引き下がり、住宅の建設に拍車がかかっています。
注目なのは、テキサス州オースティンにある3Dプリンター住宅のコミュニティです。

4軒のうち2軒は74万5,000ドル(約8,200万円)からの購入が可能であり、広さは84平方メートルから186平方メートル(25.5坪から56坪ほど)まであります。
各住宅には一般的なリビングやキッチン、ポーチや前庭、駐車場があるほか、広い住宅にはダイニングルームやランドリールームも用意されています。

3Dプリンター住宅であっても、従来の建築方法で建てられた住宅と比べてそん色がありません。世界的に住宅不足が深刻化していて、価格・供給・適応能力・デザインの選択肢などで問題を抱えていると考えられています。
しかし、3Dプリンターの技術を使えば今後の住宅業界や建設業界の近代化が一気に進むと予想されています。
日本国内における3Dプリンター住宅の事例
では、日本国内の3Dプリンター住宅の事例も見ていきましょう。
- セレンディクスの事例
- 大林組の事例
事例ごとにご紹介していきます。
事例①:セレンディクスの事例
日本では、兵庫県西宮市のベンチャー企業「セレンディクス」が国内初の3Dプリンター住宅の製作を始めようとしています。

3Dプリンター住宅なら、300万円ほどで建てられます。
安価に販売できる理由は、ロボットに作ってもらうことで最も高額な人件費を抑えることができるからです。納期が早いこともメリットで、中国の3Dプリンター住宅「Sphere」は23時間12分で全パーツが完成しています。
コンクリートでできているため、耐震性や耐熱性が高く、地面に固定しなくても重量があるから転倒のリスクもありません。
事例②:大林組の事例
日本の総合建設会社である「大林組」は、建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を取得した構造形式の3Dプリンター住宅の建設に着手しています。
建設は、東京都清瀬市内にある大林組技術研究所で行われることも、2022年6月10日に発表されました。

そもそも日本で一定以上の建物を建築するには、建築基準法を満たす必要があります。鉄筋や鉄骨、コンクリートといった指定材料を使わない場合は、建築物の安全性を個別に国土交通大臣からの認定が必要になるのです。
以上の背景から、大林組では鉄筋や鉄骨を使わず3Dプリンター用の超強度繊維補強コンクリートの「スリムクリート」や特殊なモルタルを活用した技術を開発する予定です。
3Dプリンターで住宅を作る場合にどのようなメリットが得られるのか、次で詳しく解説します。
3Dプリンターで住宅を作るメリット
3Dプリンターで住宅を作るメリットは、以下のとおりです。
- 木材の取引価格に左右されない
- 建築スピードが速い
- 人手不足が解消できる
- 曲線のあるデザインを設計できる
- 建築コストが安い
上から順番に見ていきましょう。
メリット①:木材の取引価格に左右されない
木材の取引価格に左右されないことが、3Dプリンターで住宅を作るメリットです。
3Dプリンターで住宅を作る場合、コンクリートが使われることが一般的です。木材を使わなくても住宅を作ることもできるので、木材の取引価格が住宅価格に影響することはありません。
安価な素材で造形できることから、平均住宅価格の10分の1ほどで購入できる未来が実現できる可能性もあります。
安定した価格で商品を供給するなら、3Dプリンターの導入をおすすめします。
メリット②:建築スピードが速い
3Dプリンターで住宅を作ると、建築スピードが速くなることもメリットです。
先述のとおり、住宅ほどの規模なら24時間もあれば作り終えることもあります。
そもそも3Dプリンターの建築スピードが速いのは、「24時間稼働を続けられる」「硬化速度の早い素材も使える」といった理由もあるからです。
人間ではなく機械が施工するため、24時間続けて稼働させることができます。しかも、従来の住宅とは違って型枠や鉄筋なども不要なことから、早い施工が実現できるのです。
大きな商品を多く製造するのであれば、3Dプリンターの導入も検討してみましょう。
メリット③:人手不足が解消できる
人手不足が解消できることも、3Dプリンターで住宅を作るメリットです。
従来の住宅を建設するには、数多くの専門家や職人を必要とします。一方で、3Dプリンター住宅を建設するには少ない人員だけで済むのです。
実際に、従来の住宅と3Dプリンター住宅で必要な人員を、大まかに比較してみましょう。
| 従来の住宅 | 3Dプリンター住宅 |
| ・建築士 ・現場監督 ・電気工事業 ・型枠工事業 ・地質調査業 ・大工工事業 ・管工事業 ・測量業 ・建設揚従業 ・外壁塗装工事業 ・建築工事業 ・屋根工事業 ・左官工事業 ・とび工事業 ・防水工事業 ・タイル、レンガ、ブロック工事業 ・コンクリート圧送工事業 ・内装仕上工事業 ・消防施設工事業 |
・3Dプリンター整備士 ・3Dプリンターと材料を運搬する人 ・現場監督 ・内装仕上工事業 ・外装塗装工事業 ・屋根工事業 |
3Dプリンター住宅と従来の住宅を比べると、かなり少ない人員で作れることがわかります。特に現場の作業員さんや職人さんの人員を大幅に減らせると同時に、3Dプリンターの運搬も容易です。
少ない人員で製品の付加価値を高めるのであれば、3Dプリンターを活用する方法もあることがわかります。
メリット④:曲線のあるデザインを設計できる
3Dプリンターで住宅を作ることで、曲線のあるデザインの設計ができる点もメリットです。
従来の住宅は建築方法や材料といった理由により、直線のものがほとんどです。しかし、3Dプリンターなら壁を曲面にするなど、通常の建築方法では難しい設計にも対応することができます。
3Dプリンターで使える材料は、以下のとおりです。
- コンクリート
- セラミック
- 樹脂
- 木材
主にコンクリートを使うことから、曲線のあるデザインにすることができるのです。3Dプリンターが普及すれば、さまざまな形の家が生まれるでしょう。
自由度の高いものを作るのであれば、3Dプリンターの導入をおすすめします。
メリット⑤:建築コストが安い
建築コストが安いことも、3Dプリンター住宅のメリットです。
調達する材料の価格を安くすることができるうえ、輸送や人件費といったコストも従来の住宅に比べると少ないからです。
以下は、各国の3Dプリンター住宅価格の目安です。
| 価格 | 広さ | 企業名 | |
| アメリカ | 約45万円 | 180~240㎡ | ICON |
| ロシア | 約115万円 | 38㎡ | アピスコア |
| 日本 | 約300万円 | 10㎡ | セレンディクス |
日本のプリンター住宅価格が他国より高額な理由は、厳格な建築基準にあります。
3Dプリンター住宅の材料は、コンクリートが中心です。
しかし、日本の住宅にコンクリートを使う場合は、鉄筋を組み合わせないと許可が下りにくいのです。コンクリートは地震の引っ張る力に弱いからです。
ただし、大林組の事例では、3Dプリンター用の特殊モルタルとスリムクリートの2種類を使うことで、鉄筋なしでも強度のある構造物を建築することができます。
安いコストで製品を作るのであれば、3Dプリンターの導入をおすすめします。
3Dプリンター住宅に関するよくある質問

以下は、3Dプリンター住宅に関するよくある質問です。
- 3Dプリンター住宅は、いくらで購入できる?
- 3Dプリンター住宅は、どのくらいの期間で製作できる?
上から順番に見ていきましょう。
Q1:3Dプリンター住宅は、いくらで購入できる?
日本で購入する場合は、300万円ほどになると言われています。
現在、兵庫県西宮市のベンチャー企業「セレンディクス」や総合建設会社の「大林組」などが3Dプリンター住宅の開発に着手しています。従来の住宅は建売住宅で平均3400万円台なので、10分の1以下の価格で購入できます。
Q2:3Dプリンター住宅は、どのくらいの期間で製作できる?
3Dプリンター住宅は、複雑な構造でなければ約24時間で製作できます。機械なので「休まずに稼働できること」や「硬化速度の早い素材も使用できる」ことが製作スピードの速さの理由です。
まとめ
今回は、3Dプリンターで作った住宅の活用事例や料金などを解説しました。
以下に、今回お伝えした内容をまとめました。
- 住宅の購入は30年ローンが一般的で、現代ではリスクが高い
- 注目されているのが3Dプリンターで作った住宅
- 今後、日本国内なら300万円前後で購入できる予定
- 日本ではセレンディクスや大林組が3Dプリンター住宅を開発中
- 3Dプリンター住宅なら木材価格に左右されず安価に製作できる
住宅に限らず、3Dプリンターは新たなビジネスに対応できるツールといえます。新しい事業を展開するのであれば、同業他社が導入する前が好ましいといえるでしょう。
当社は家庭用から業務用までの樹脂3Dプリンターを取り扱っており、建築模型であれば製作することができます。そのため、3Dプリンターで製作した建築模型を見ながら商談を進めるお手伝いなら可能です。
製品の疑問などございましたら、お気軽にお問合せください。